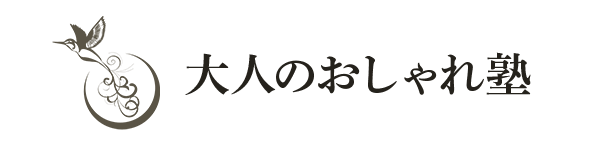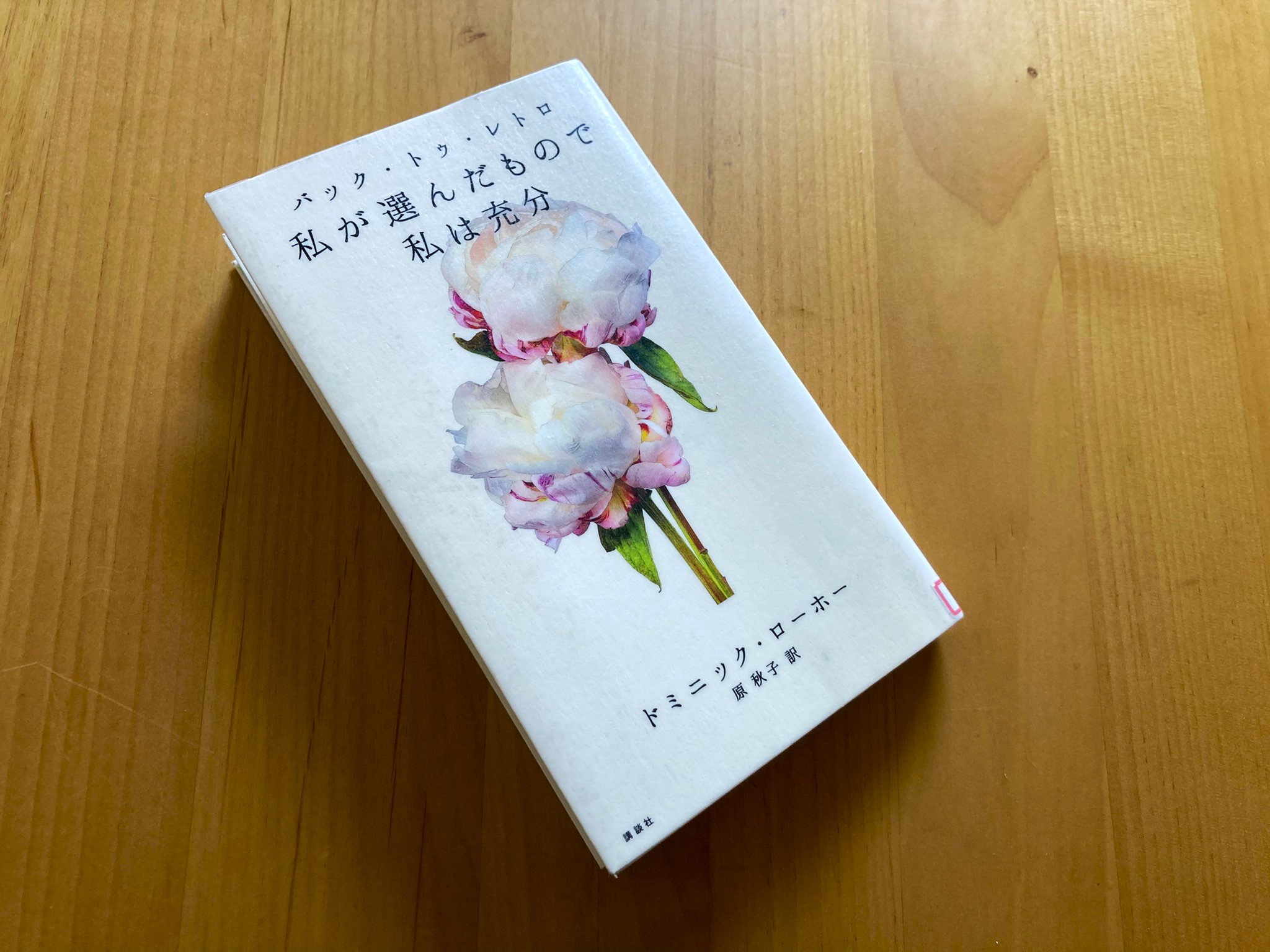今日は先日、地域の公民館(図書室)で借りた本のお話です。
著者は2016年に『シンプルに生きる』がベストセラーになったフランスの著述家、ドミニック・ローホー。
『シンプルに生きる』はとても面白かったので、彼女の本なら読んでみようと思いました。
私が選んだもので私は十分 (2018年 講談社)
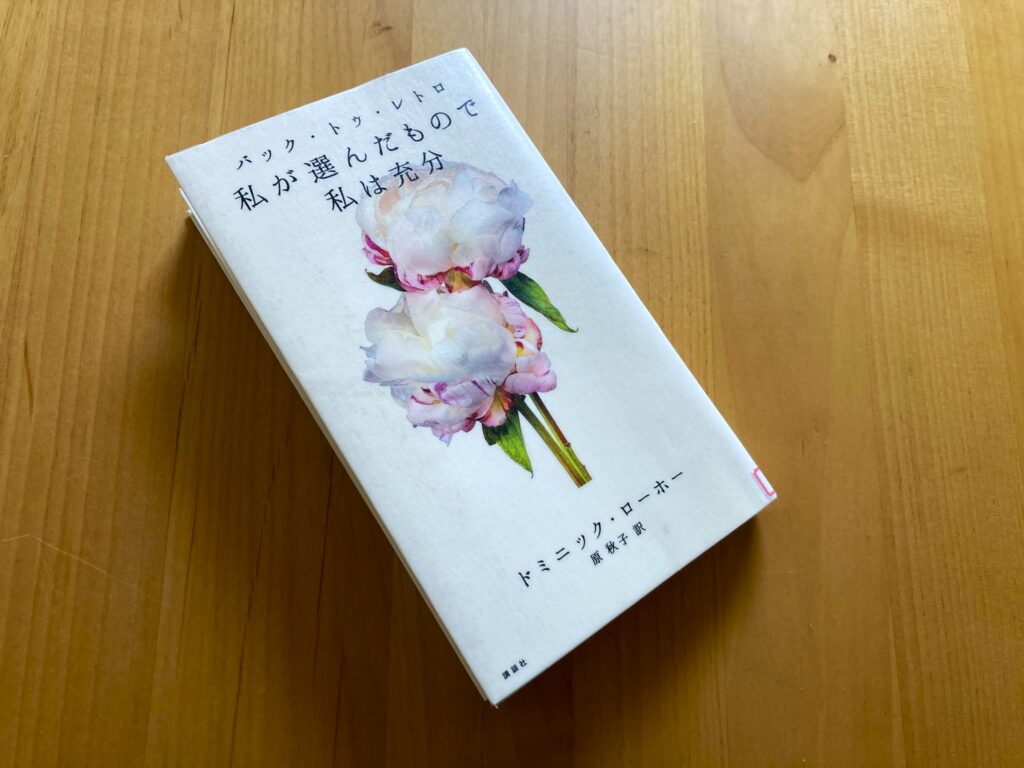
内容的には『シンプルに生きる』の二番煎じな感じはありますが、それでも第2章の<幸せをつくる選択肢>では、考えさせられる部分が多々ありました。
まずp.40の「選択肢が多いほど不安も多くなる」
私たちは選択肢が多いほどより良いものが選べそうに思いますが、じつは反対で、選択肢が多いほど判断に迷いが生じて、結局は買わずに終わることが多いという記述です。
このことは彼女の著作以外でも目にすることは多いので、特段驚くには値しないかもしれませんが、続く文章がふるっています。
たくさんの選択を避けるための秘訣は「比較しないこと」です。満足度の基準を90%で甘んじるようにしましょう。(p.48)
もの選びは「まあまあOK」で手を打つことが大事で、そうして受け入れることが心に安らぎをもたらします。(p.48)
「まあまあで手を打つ」ってなかなかキャッチーなフレーズです。
さらにこう思うことが大切だとか。
私が選んだもので私は充分(p.49)・・・
なるほど・・・そう思えたら心は安らかでいいですよね。満足感さえ漂っています。
じつは私も限られたもので幸せを感じることができた時期があったのです。
それは4年前に大動脈解離(スタンフォードA型)の緊急手術を受け1か月後に退院した頃。当時は歩行もおぼつかなく、数か月してようやく近所のスーパーに短時間なら行けるようになったのですが、その時、店内にあるダイソーで買ったのがこちらのニットキャップ。涙が出るほど嬉しかったです。

たった100円ですが、私には宝物のような存在でした。買い物に行けた嬉しさ、選択肢が限られているからこそ得られた喜びだったかもしれません。
今は自由に買い物に行けるようになりましたが、ほどほどのもので満足するという指向性は年齢のせいかもしれませんが備わってきたように感じます。それが特段良いことだとは思いませんが、ローホー的には良いことなのかもしれません。
ですがここで注意しなくてはならないのは、ローホーは、第3章の<こんなものたちと暮らしたい> で、納得のいく買い物をすることが大事だとしているのです。
第2章では「まあまあで手を打て」と言っているのに第3章では「質のよくないものを買うほど私は金持ちでなはない(p.56)」「品質のよいものは修理して長く使え、大量消費によるゴミや自然破壊といった環境破壊から私たちを守ります。(p.57)」と。
確かに品質のよいもの、流行に左右されないもの、ずっと一緒にいたいと思えるものに囲まれて生活するのは素晴らしいに違いありませんが、それって確かな審美眼と、取捨選択の果てに得られるものではないでしょうか。「まあまあでOK」とは程遠い世界のように思われます。
第2章と第3章では、言っていることに齟齬(そご)があるのですね。そこが大変残念です。
そう思いながら(不満つらつらで)読み進めていったのですが、最後、第10章でハッとする文章に出会えました。
どうしたら「最高の自分」になれるか、という問いかけは自分をミスリードすることもあります。(p.149)
もっと綺麗になりたい、もっと素敵になりたい、どうやったらそんな「最高の自分」になれるかの問いかけや努力が、往々にして人を誤った方向に導いてしまうというのですね。
これはなかなか深い言葉です。
強く願うほどに自分を苦しめ「ほどほどで満足する」幸福感からその人を遠ざけてしまう、ということでしょう。
途中、第3章で理論の破綻を感じましたが、最後になってようやく繋がったというか、私が選んだもので私は充分、と思える生き方の大切さを学びました。
「ほどほどで満足する」とは幸福感へのひとつの道筋なのですね。